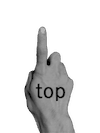Contents -目次-
古代ギリシャ・ローマの美術史の概要を的確に知るにはちょうど良い一冊
前回の記事『読んだ本|『ギリシア・ローマ名言集』柳沼重剛・著』に引き続き、古代ギリシャ、ローマに関連した本を読んでいます。
そもそも、古代ギリシャに興味を持ったきっかけは、そのあまりに鮮烈な造形で無二の存在感を放つ、美しい彫刻に魅かれたからでした。
『クリティオスの少年』紀元前480年ごろ
ちょうど現在(2016年9月)、東京国立博物館で「特別展 古代ギリシャ ー時空を超えた旅ー」が開催されていることもあり、その予習も兼ねて、一度流れをおさらいしたかったので、同書を購入。
とても働き者のおじさんがやっている、いつもの古本屋でたまたま見つけました。
実はこの『ギリシア・ローマの美術』(岩波書店)は本来はセットのもので、全8冊のうちの第1巻。それがバラで売られていました。
西洋美術の流れを全8冊を通して眺めていく趣旨のシリーズの、まさに始まりである古代ギリシャの美術、そしてその古代ギリシャ美術を崇拝し受け継いだローマの勃興から衰退までの流れを通して見ていくのが本書の趣旨。
なんとなく表紙の感じが良かったので、買ったのですが、買ってよかったです。
ただ歴史をなぞるだけでなく、資料として的確な図版が本文にの流れに合わせてその都度参照できるように工夫してレイアウトされています。内容が多すぎず、かといって少なすぎず、古代ギリシャ・ローマ美術の流れ、概略を的確に知りたい自分にはちょうど良いヴォリュームの一冊でした。
私は特に彫刻に興味があるのですが、新たな発見があり面白かったです。
そもそもギリシャの彫刻の源流はエジプトの彫刻なんですよね。
<古代ギリシャ人彫刻家の挑戦>
ここで面白いのは、エジプトとギリシャの彫刻への取り組む姿勢の違いです。
エジプトは数千年近く、その彫刻の基本的な造形を変更することはありませんでした。上のb、cの像を見比べていただくとわかると思います。
古代では、今よりもずっと目に見えないものへの恐れが強かったため、むやみな変更を嫌うことがあったようです。今までの形を変えたりするような変更は、神への怒りをかうかもしれないと思われていたのです。
ところがギリシャの人々は違いました。
エジプトの彫刻に感銘を受けたギリシャの人々が、その技法を取り入れて作り始めたのがギリシャ彫刻の始まり。その初期には彼らも挑戦への恐れはあったのかもしれません。
しかし、ギリシャ人は異なる美へのこだわりを持っていたようです。
その彫刻において、彼らは彼ら自身の内的な美の原理を追求しはじめるのです。数百年をかけて、少しづつ改変を加え、究極の美しい彫刻にたどり着く彼らのあくなき挑戦が、あの大変素晴らしい彫刻を生み出したのですね。
重要なのはギリシャ美術全体を通じて、「改変ー問題の出現ー解決ー別の問題の出現」というサイクルが普遍的に見られ、またその彼らの果敢な挑戦こそが高いレヴェルの造形美を生み出した、ということです。
そして、その冒険心とより素晴らしいものを求める高潔な探究心は、その後の西洋美術に深い影響を与えたことは間違いなさそうです。
また美術のみにとどまらず、現代まで続く我々の、文明世界の発展の根幹となったのではないでしょうか。
彼らの挑戦がなければ、現在我々が目にすることができる素晴らしい彫刻や、もしかしたらテクノロジーも?今とは全く違うものになっていたのかもしれません。
「クリィティオスの少年」

「クリティオスの少年」
「Kritios Boy」
https://en.wikipedia.org/wiki/Kritios_Boy
(wikipediaより転載)
ギリシャ彫刻の発展の様子を少し追って見てみましょう。
直立不動の、原始的なクーロスから、偉大な挑戦への一歩を踏み出した作品がこちらの「クリティオスの少年」という作品。紀元前480年ごろの作品です。
直立不動で硬直気味の初期のクーロス像に比べとても自然です。
より自然な肉体の表現を目指し、ちょっと首を横に向け、重心を移動させただけですが、偉大な挑戦だったのです。
「アルテミシオンのゼウス」
こちらは石像彫刻より後に登場した新しい素材、青銅(ブロンズ)の像。
この「アルテミシオンのゼウス」(紀元前475年ごろ)のように青銅であれば自由で大胆なポーズを持つ彫刻が作れるのですが、これを石でやると腕のあたりで折れます。
とてもかっこいいポーズですけどね。
この青銅像のもつ躍動する生命感に打たれた彫刻家は、石像でも可能な限り大胆なポーズに挑戦するという冒険を始めるのです。
「ディスコボロス」
彫刻家ミュローンによる、有名な「ディスコボロス(円盤投げ)」(紀元前450年頃)は石像で躍動感を追求した作品の一つの到達点と言えます。当時から大変な評判で、後代のローマ人にも高く評価され、数百年の時代を経てなお模刻が作られるほどでした。
一瞬を捉えた躍動的で、素晴らしい作品です。
よく見ると足のそばに支えがあります。石なので、割れる恐れがあったため、樹木を模した支えが必要だったのです。
ギリギリまで石像で表現できうる限りの、極めて微妙な均衡を追求したことが伺えます。
「ドリュフォロス」
数々の試みへの解決は、彫刻家ポリュクレイトスの「ドリュフォロス」という作品によって、もたらされました。紀元前440年ごろの作品です。
ここで有名な「コントラポスト」と言う言葉が出てきます。
トルソの収縮した片側と、伸長したもう一方との対照が、体に動きのある均整を与える。これは左右がほぼ鏡像関係にあるクーロスの静的なシンメトリーとは大きく異なっている。それぞれがトルソに対応して、結び付く緊張と安らぎの状態にある手足の対照を「コントラポスト」と呼ぶ。
このコントラポストという表現が、ギリシャ彫刻における一つの到達点となります。完成された調和をもたらすコントラポストは、その後の美術の歴史でも、何度も用いられることとなります。
この「ドリュフォロス」がつくられてから約1500年後の、ゴシック時代においてもコントラポストはとても高く評価され、聖母像などに優雅さと気品を与えるために用いられたことが知られています。
どの角度から見ても、調和し、なおかつ動的でもあるコントラポストの用いられたドリュフォロス像によって、ついに問題が全て解決されました。
なんでもないようなポーズに見えますが、多大の技巧と工夫が凝らされているのです。この高度な表現によって完全な調和が得られたのです。
それにしても、石を彫るのって大変なんだなと思いました。
以前、彫刻家・舟越保武の展覧会を見に行った時に、学芸員の方に「船越先生の石像にサインはあるのですか」と尋ねたことがあるのですが「石像はちょっとの加減で割れてしまうことがあるので、サインを入れることもあるがむやみに刻むことはない」と、そんなような事を答えていただいた事を思い出しました。
ギリシャ彫刻に興味があったので、初期のギリシャ彫刻の話しばかりになりましたが、同書の他の章ではギリシア神殿などの建築、赤像式/黒像式技法による陶器、絵画なども余すことなく詳述されています。
そのギリシャ美術を崇拝し、また後代において偉大な支配者となったローマ人たちの美術がどうであったかも歴史をたどりながら的確に見ていくことができます。
西洋美術の源流と言われる、古代ギリシャ・ローマの美術。
いろいろな紹介本はありますが、見にくかったり、要点が不明確だったりすると、なんとなく頭に入りづらいものですが、同書は私にはちょうど良かったです。これ一冊で全部オッケーというわけでは決してありませんが、まずは的確に概要を知りたいという方にはとてもオススメの一冊です。
| ギリシア・ローマの美術 (ケンブリッジ西洋美術の流れ 1) |
||||
|