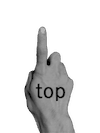Contents -目次-
日本の労働生産性が低い、という問題への疑問

なぜ日本の労働生産性が低いのか以前から疑問でした。
個人的には、正直なんとなく直観に反するような感じがあって、日本の生産には非効率な部分はあるけれど、とはいえ諸外国と比較して、決して労働生産性が低いという事はないのではないか、と根拠もなく考えていました。
周りにはものすごく優秀で勤勉な人ばかりなのに、なぜ日本は労働生産性が低くなってしまうのだろう?とても不思議。
この機会に、私なりに調べてみました。どうして日本の労働生産性が低いのか、みていきましょう。
つい、ダラダラ書いてしまうので、先に私なりの結論を書いておきます。
ここ20年近く、日本はデフレで経済成長していません。結局その不景気がもたらす、マイナスの影響の一つとして現れるのが労働生産性の低下ということではないかと思います。ある意味それだけのことにすぎないとも言えるかもしれません。労働生産性という指標にとらわれずに、根本的な経済成長をもっと重視する必要があります。GDPが大きくなれば勝手に労働生産性は大きくなります。なぜなら「労働生産性=購買力平価GDP/就業者数」だからです。他の先進国と同じ水準の成長をすれば、労働生産性もある程度上がると思います。もし日本の労働生産性の改善を重視するならば、よく言われる経営体質改善などのミクロの方法だけではなく、現在のデフレ下の日本においてはマクロ経済政策の重要性こそもっと指摘する必要があると思います。
労働生産性の計算方法
前回の記事で労働生産性を自分なりに計算してみました。
「日本生産性本部」によると、
「労働生産性を国際的に比較するにあたっては、付加価値をベースとする 方式が一般的であり、労働生産性を
労働生産性 = GDP / 就業者数
(※GDPは購買力平価(PPP)により換算されたもの)
として計測を行っている。」
日本生産性本部 労働生産性の国際比較PDFより http://www.jpc-net.jp/annual_trend/annual_trend2015_3.pdf
ということで「 労働生産性 = GDP(購買力平価換算) / 就業者数」です。
なぜ労働生産性が重視されるか?

ではなぜ労働生産性、そしてそれが低いことが問題になるのでしょうか?
それは、生活水準に直結するからではないでしょうか。「労働生産性が低い」と言われると、私なんかはつい、よく考えずに暗黙の前提で、生産性が低いのは悪いことだ!と思い込んでしまうのですが、結局、労働生産性が低いと、GDPが低くなる。なので、労働生産性が低いことがしばしば問題視されるのでしょう。
つまり、
労働生産性 = GDP / 就業者数
(※GDPは購買力平価(PPP)により換算されたもの)
なので、
↓
GDP = 労働生産性 * 就業者数
(※GDPは購買力平価(PPP)により換算されたもの)
まあ一応こうなります。労働生産性が低いとGDPが低くなりますよね。生産性が高く、同じ生産量を短時間で実現できれば、より多くの消費ができます。生産性の上昇は我々の生活を裕福にします。ではGDPが低いことは問題なのでしょうか?当然生活水準に直結しますから、それは大きな問題だと思います。
GDPとは国内総生産の略です。マンキュー先生の経済学のテキストによると、
国内総生産(GDP)は、一定期間において、一国内で生産されるすべての最終的な財やサービスの市場価値である。
N・グレゴリー・マンキュー「マンキュー経済学Ⅱ マクロ編 (第3版)」p.139
と定義されています。ものすごく簡単にいうと、GDP=その国の経済の大きさ、になるかと思います。GDPの大きさは、その国の豊かさや生活水準をダイレクトに反映するということですね。
ちなみに、2014年の各国の購買力平価GDPは、
- 日本 4631
- アメリカ 17419
- 中国 18030
- イギリス 2524
- ドイツ 3689
(10億米ドル)
(総務省統計局 世界の統計 2016 第3章 国民経済計算より http://www.stat.go.jp/data/sekai/pdf/0116.pdf#page=59)
と言う感じになっています。アメリカはダントツですね。中国もとても成長しています(数値の信ぴょう性の問題も指摘されていますが)。とはいえ、単純にこのGDPの大きさだけで、一国の経済の良し悪しが全てわかるわけでもありません。様々なデータを参考にしながら経済学者は経済を見ています。例えば、GDPをその国の人口で割った、「一人当たりGDP」などの指標もよく使われます。
日本の労働生産性の現状
次は労働生産性の現状を見てみます。各国の「購買力平価GDP / 就業者数」を計算して、労働生産性の高い順に並べていったものが、この図です。
2014年度の日本の労働生産性は21位、そしてG7(米、独、日、カナダ、英、伊、仏)の中では最下位です。
労働生産性本部 日本の生産性の動向2015年度版 概要 http://www.jpc-net.jp/annual_trend/
労働生産性が低い一番の原因

ここが一番の問題です。
原因と結果を慎重に見る必要があります。先の労働生産性の計算で見ましたが、
労働生産性=GDP/就業者数ということは、
GDP=労働生産性*就業者数でもあります。
労働生産性が低くなるとGDPが低くなる、これは問題だ!ということで、「労働生産性が低い」と言われる時にはしばしば効率をあげろ、生産性を上げろ、などと言われるのですね。
しかし、私はそれは一面的な見方すぎるのではないかと思います。
繰り返しになりますが、逆に言えば、
GDP=労働生産性*就業者数
ということは、
労働生産性=GDP/就業者数です。
効率を上げることももちろん必要ですが、労働生産性をあげるには、GDPを大きくすればいいということでもあるはずです。コインの裏表のような関係?
GDPも就業者数もマクロ経済で扱うトピックでもありますから、マクロ経済の視点も無視はできないはずです。
そして私には、そのマクロ経済環境における、長引くデフレによる日本経済の不調が、労働生産性が上がらない一番の原因に思えます。
労働生産性はマクロ経済の景気動向と無関係ではない

労働生産性が低いから、不景気なのではありません。デフレで不景気だから労働生産性が結果的に、余計に低くなってしまうのです。
前章で見たように、労働生産性はGDP/就業者数です。
そして「GDP」も「就業者数」もマクロ経済で扱う内容です。すなわち労働生産性はマクロ経済の動向によっても変動する数値です。少なくとも、景気動向とは無関係ではないはずです。
景気が悪ければ、GDPは拡大せず、労働生産性も低くなるはずですよね。日本は1990年代半ば以降、20年近く長期にわたるデフレです。デフレとは長期にわたって物価(個別の品物ではなくて、全ての品物の物価の平均である一般物価)が下落していくことを言います。
ではなぜ日本はデフレなのでしょうか?決して、日本の経営体質や働き方の非効率が原因ではありません。
マンキューのマクロ経済学のテキストに「インフレーションは悪いが、デフレーションはおそらくさらに悪い」という章があります。そこにはこうあります。
アメリカの歴史を振り返ると、最近はインフレーションが常態となっている。しかし19世紀後半や1930年代始めのように、物価が低下したこともあった。さらに日本では近年全般的な物価水準の低下を経験している。
中略
おそらく最も重要なことは、デフレーションがマクロ経済の全般的な不調によってもたらされることが多い点であろう。のちの諸章で見ていくように物価の低下が生じるのは、金融引き締めなど何らかの出来事が経済の財・サービスへの総需要を低下させる時である。こうした総需要の低下は、所得の低下や失業率の増大につながりやすい。つまり、デフレーションは、より深刻な経済問題が起こっているという兆候であることが多いのである。
N・グレゴリー・マンキュー「マンキュー経済学Ⅱ マクロ編 (第3版)」p.393-394
ものすごく大事なことが、簡潔に書いてあります。
『物価の低下が生じるのは、金融引き締めなど何らかの出来事が経済の財・サービスへの総需要を低下させる時である。』
そうです、”金融引き締めなど何らかの出来事”がまさに日本に起こって”経済の財・サービスへの総需要を低下させ”ているのです。日本では過度な金融引き締めが20年近く行われてきました。
その結果、深刻なデフレによる長期停滞が起こっています。そしてデフレによる総需要の低下は、所得の低下や失業率の増大をもたらしました。
総需要が低下し、所得が低下すれば、いくら効率を上げて生産しても売れませんよね。欲しがる人がいないのだから。生産性が高く、たくさん生産できる、というのは一方でたくさん消費できる、つまり多くの需要があることの裏返しです。こういった、マクロの総需要についても、触れるべきなのにほとんどの労働生産性についての記事は効率や働き方の改善などの「供給」の問題しか取り上げていません。
なぜその辺が考慮されないのが、不思議ではあります。マンキュー先生の教科書を読んだだけの私が言うのもなんですが、日本ではマクロ経済についての見識を元にして、公で発言される識者がとても少ないのは何故なのでしょうか?
「供給」があれば「需要」もあるはずです。「需要」について、述べられている記事が少ないのはかなりアンバランスに私には思えます。
労働生産性についてのいろんな記事を批判的に見てみる

さて、原因がわかったところで、次はこの日本の労働性の低さについて取り上げている記事の代表的なものを批判的に見ていきたいと思います。個人的にはこれらの記事の大半は大いに不満な内容ばかりです…。
ハフィントン・ポスト<勤勉さだけでは改善できない日本の低い労働生産性 | ロッシェル・カップ>
www.huffingtonpost.jp/rochelle-kopp/labor-productivity_b_8865802.html
『これまでの経済的な課題と違って、日本の労働生産性は「もっと頑張る」だけでは解決できない。真の課題は、どのように頑張るか、言い換えれば労働力をどう賢く活かすか、なのである。私には、日本はせっかくの優秀な労働力を非常に非効率に使っているように思える。無駄使いと言っても過言ではないだろう。日本は、自国で調達できる自然資源が少ないこともあり、労働力をうまく使うという意味で世界のリーダーになるべきだ。』
ダイヤモンドオンライン<「日本人の生産性」は先進国で19年連続最下位 非効率なホワイトカラーの働き方はどう変わるべきか>
http://diamond.jp/articles/-/54160?page=1
『なぜ日本企業はこれまで生産性を上げることができなかったのでしょうか。2つの理由が考えられるのですが、1つ目の理由として、社員がどのように働いているか、何にどれほどの時間を要しているかという、ログ(データ記録)が取れなかったことが挙げられます。
中略
もう1つの理由は、なんでしょうか。それは、経営者の意識が「社員の生産性向上」に向いていなかったことです。もちろん経営者の意識改革は難しいことです。しかし、データで社員の働き方が可視化できれば、考えるきっかけにもつながるはずです。』
日本生産性本部<日本の生産性の動向>
http://www.jpc-net.jp/annual_trend/annual_trend2015_2.pdf
『名目賃金を今後も上昇させるには、 実質労働生産性のさらなる引上げが重要になることを示している。』
日本人はなぜ学力が高いのに生産性は低いのか | 永井俊哉ドットコム
https://www.nagaitoshiya.com/ja/2015/japanese-labor-productivity-levels/
『日本は、先進国で最高の人材を持ちながら、先進国で最低の労働生産性しか出せていないという最悪のシステムを長期にわたって放置し続けている。日本人は国内の待遇が悪くても海外にはなかなか逃げないし、日本は経済大国であるため簡単には破綻しないから、政治家たちはあまり深刻にはとらえていない。しかし、私たちは、この情けない状況を変えるために努力しなければならない。』
労働生産性が34か国中21位の日本と2位のノルウェー その違いは労働時間ではなく「働き方」にあり
http://blogos.com/article/178881/
『生産性の高さの違いには、両国の「働き方」の違いがあるようだ。始業・終業時刻が決まっている企業は、日本では65.5%だったが、ノルウェーは17.5%。多くの企業が「フレックス」や、より自由度の高い「フルフレックス」制度を取り入れ、従業員の自己裁量で労働時間を決められるようになっている。また、働く場所を問わないリモートワークも、日本の企業ではまだ20.9%しか認められていないが、ノルウェーでは77.5%の企業で認められている。』
「日本 労働生産性 低い」と検索すると上記の記事が並びます。
目を通してもらえば分かりますが、これらの記事のほとんどは「働き方」に焦点を当てています。効率化、改善、労働環境、改革、思想、日本の経営体質、労働習慣、など様々なトピックが並びますが、どの記事も何かにつけては、生産性を上げろとしか述べられていません。
しかし、これは見方としてはあまりに一面的すぎると思います。
確かにわかる!というものもありますけどね。「なんでこんな無駄な仕事に付き合わなきゃいけないんだ!怒」とか、職場でありますね。でも、そんな時でもなんとなく昔からこうだったから、とか、そんなんで現状維持とか、嫌ですけどね、ありますよね。改善も確かに必要な部分は山ほどありそうです。
日本の労働生産性が低い原因って、働き方が非効率だから?しかし、果たしてそれだけなのでしょうか?私は違うと思います。
先に見たように、デフレも大いに関係しているはずです。そのあたりをスルーして、やたらに改革、改善をおしつけるような記事ばかりが並ぶのは、あまり良い事ではない気がします。少なくとも、効率性アップなどの供給面を大いに問題にするならば、同時に一方の需要の問題もそれと同等、あるいは現状デフレ不況下の日本であれば、さらにそれ以上に積極的に扱わなければ、不十分と言わざるを得ないのではないでしょうか?
マクロ経済のデータで労働生産性を見てみる。

マクロのデータも見てみたいと思います。
労働生産性が話題になる時に、よく用いられるのがOECD(経済協力開発機構)データです。
(OECD (2016), Labour productivity and utilisation (indicator). doi: 10.1787/02c02f63-en (Accessed on 07 October 2016))
再確認になりますがこのデータの図でも、明らかにグラフ中で日本は下位に位置していることが見てとれます。
ちなみに、日本の労働生産性は主要先進国であるアメリカ合衆国、イギリス、
実は、労働生産性の他にも、日本がG7の中で最低水準にある指標はご存知でしょうか?
世界全体のGDPに占める各国の構成比
労働生産性の他に、日本がG7の中で最低水準にある指標、それは、GDPの伸び率、経済成長率です。
日本は経済の成長率が主要先進国の中で最低レベルなんですね。2000年代以降、主要先進国は平均して年2パーセント台の成長率ですが、日本だけマイナス成長です。
世界の国内総生産(名目GDP,構成比)を見てみます。特にG7だけを白抜きにしました。

総務省統計局 世界の統計 2016 第3章 国民経済計算 http://www.stat.go.jp/data/sekai/pdf/0116.pdf#page=59
日本だけ大きく落ち込んでいます。
世界全体のGDPのうち、各国がどれだけの割合を占めるかという表ですが、他の国に比べて、日本だけ明らかに低下の幅が大きいです。他の国は多少幅はありますが、世界全体のGDPに占める割合は年を通じてそこまで変化していませんが、日本だけその存在感を低下させています。他国のGDPの成長率に対して、日本だけ成長率が低いのです。
繰り返しますが、決してその原因は労働生産性が低いから、だけではありません。デフレが大きく関係しています。
物価上昇率の推移
また、物価上昇率もG7各国で最低です。当然、デフレなので物価が下落しています。
IMFのデータベース「World Economic Outlook Database, October 2016」でG7各国の消費者物価指数(年平均値)の推移を見ると、日本だけマイナスの年が出てきます。内閣府では「BIS(1999)やIMF(1999)が景気判断とは切り離して「少なくとも2年間の継続的な物価下落」 をデフレと定義している」とあります。
G7の消費者物価指数(年平均値)の推移 IMF「World Economic Outlook Database, October 2016」http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=85&pr.y=6&sy=1990&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=156%2C158%2C132%2C112%2C134%2C111%2C136&s=PCPIPCH&grp=0&a=
マネタリーベースの残高の推移
こちらの図を見ると、日本だけ極端にマネタリーベース残高が低い状態で推移していることがわかります。マネタリーベース残高が低いということは通貨供給量が少ないことを表します。先に「デフレの原因」について触れましたが、金融引き締めによる中央銀行の通貨供給量の相対的な低下はデフレの原因です。
就業者数
就業者数はどうでしょうか?
国の人口で言えば、日本は世界10位ですが、就業者数で言えば実は世界2位です。

IMF「World Economic Outlook Database, October 2016」 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=17&sy=2012&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C946%2C122%2C137%2C124%2C546%2C156%2C181%2C423%2C138%2C935%2C196%2C128%2C142%2C939%2C182%2C172%2C359%2C132%2C135%2C134%2C576%2C174%2C936%2C532%2C961%2C176%2C184%2C178%2C144%2C436%2C146%2C136%2C528%2C158%2C112%2C542%2C111%2C941&s=LE&grp=0&a=
こちら世界経済のネタ帳 世界の就業者数ランキング http://ecodb.net/ranking/imf_le.htmlではIMFのデータをもとに、世界各国の就業者数がランキングされています。1位はアメリカ、2位は日本、3位はドイツ、4位はイギリス、5位は韓国、6位はフランスと続いていきます。
日本は就業者数が世界で第2位なのに、他の国の平均的な成長率に比べて低いGDPの伸び率であれば、相対的に労働生産性は大きく低下してしまうことになってしまいます。労働生産性=GDP / 就業者数ですからね。むしろ就業者数が大きければ大きいほど、GDPの増減が数値に与える影響は大きいと言えそうです。
まとめ
なぜ日本の労働生産性は低いのか?それには二つ原因が考えられます。
- 一つは、よく言われるような労働や仕事の非効率さがもたらすミクロの領域での問題。
- もう一つは現状においてはより重要なマクロの問題で、日本はデフレ不況により他国と比較して経済成長率が低いため。
色々調べれば調べるほど、労働生産性の低さは、一番の問題ではないと思えてきます。むしろ、日本のデフレという経済状況を考慮せずに労働生産性だけを取り上げることは、問題の根幹から人々の目を逸らせてしまうような気すらします。「労働生産性の低さ」は、長引く不況がもたらした一つの表面的な結果にすぎません。現状であれば、一番の問題はデフレによる不況です。日本経済が置かれたこの状況でむしろ、デフレであるという状況を考えずに、労働生産性に注目することは、いびつな見方をもたらしてしまうかもしれません。
デフレから脱却し、普通の先進国なみの水準の経済成長を続けている状態であれば、まだ意味がある指標かもしれませんが、現状はそうではありません。普通の先進国並みの成長を果たし、それによる十分な需要があってこそ、よく言われるような、効率化や働き方改革などの、生産性の改善という議論が成り立つのではないでしょうか?
労働生産性が低いからデフレで不況が続いているのではありません。デフレで不況だから労働生産性も結果として低いのです。
原因と結果が逆になったような感覚ですが、何かにつけて、この手の議論ははびこっているような気がします。デフレ不況という状況を抜きにして、やれ働き方が悪いだの、効率だの、取り上げられるのは常に供給についての話題がほとんどです。日本人の努力不足?働き方の問題?そこだけを強調するのは、なんだかすごくアンバランスです。
供給の反対には需要があるはずです。需要不足のせいで、生み出された財・サービスが高く評価されなければ、付加価値は上がりません。原因はデフレのもたらした需要不足。需要がないところでいくら生産性を上げても限界があります。需要不足が、労働生産性の低さ、ひいては問題の根幹である日本経済の長期停滞を許すことになっている一番の問題だと私は思います。
私も勉強中ですが、もし経済学について基本的なことが知りたければまずこちらがおすすめです。少し古いですが内容は普遍的に有用なものばかり。ミクロ、マクロの重要なトピックをコンパクトにまとめてあります。
| マンキュー入門経済学 | ||
|
| by ヨメレバ |
私はマクロ経済についてもっと知りたかったので、入門編に続いてこちらのマクロ編を買いました。失業、雇用の問題、金融、、、本当に素晴らしい知見がたくさん掲載されています。ぜひ。
| マンキュー経済学 II マクロ編(第3版) | ||||
|