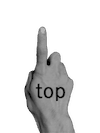| まんがでわかるピケティの「21世紀の資本」 (まんがでわかるシリーズ) | ||||
|
内容(「BOOK」データベースより)
文鳥の飼い主が集まる交流会で知り合った貧乏OLの月村ひかりと大資産家の娘、天ノ川恵。2人の間に厳然と横たわるのは、ピケティが描いた「持てる者」と「持たざる者」の格差の壁。個人ではなす術もない大きな経済の趨勢を実感しながら、それでも流されたくないと願うひかりの選択とは―?いま最も熱い経済書の要点が、広がる格差の理由を示すr>gの意味がまんがでわかる!原書を訳した山形浩生が監修!
Contents -目次-
山形浩生さん監修なので安心して読めます
ピケティの原著は時間的にも、内容的にも今の私にはハードルが高すぎるので、まんがだしボリュームもそんなにないしちょうど良さそう!ということで購入。
とても満足できる内容でした。集中して、一気に読めましたね。まんがならではのわかりやすさで、必要なエッセンスはつかめたと思います。今はブームも少し過ぎたので、アレですが、もし誰かに聞かれたら簡単に説明できるくらいにはつかめたかと思います。
アマゾンで「ピケティ まんが」などで調べると分かりますが、実はこの手のまんが版「21世紀の資本」は他にも幾つかあります。
ただ他のものより圧倒的に、この本が良いのは監修を山形浩生さんがされていることです。
山形浩生さんは、数々の経済学関連のエッセイや古典も翻訳されている方で、ケインズ「雇用、利子、お金の一般理論」やクルーグマン「さっさと不況を終わらせろ」などその仕事は多岐にわたります。(あとコンピューター関連や、そもそも開発援助がご専門のようです。)
そして何より私の大好きな『この世で一番おもしろいミクロ経済学 』&『この世で一番おもしろいマクロ経済学 』も翻訳されています。
私はこの二冊の大ファンなのです。友達にも貸したりして、友達も気に入ってくれてました。とても面白かったですし、この二冊もまんがなんですよ。なので今回のピケティまんがも山形さんがらみで安心して購入しました。
そもそも原著のピケティの「21世紀の資本」の日本翻訳版は山形浩生さんですしね。変なイデオロギーや経済学的な間違いはまずないですし、内容もわかりやすくまとまっていました。
ちょっとブームが去った後なのであれですが、まあ教養としてポイントを押さえておきたかったのです。その点では、まさにぴったりな内容。
まんがの本編に添えて、各章ごとに、ピケティの主張の根拠となる図版を的確に示しながらの程よいボリュームの解説があります。まんがで楽しみながら、この解説でより理解を深める、という流れですね。まんがのストーリーが途切れるのがアレな方は、最初にまんがを一気読みして、それから解説だけをまとめて読んでも良さそう。
従来の経済学への挑戦

「トマ・ピケティ」
https://ja.wikipedia.org/wiki/トマ・ピケティ
wikipediaより転載
世界各国、200年以上の徹底的にデータを調べあげ、15年かけて経済学のエリート、ピケティが達成した成果が「21世紀の資本」。データが多いからなのでしょうか?原著のちょっと後ずさりしてしまうようなその分厚さとは対照的に、実はピケティの主張は割とシンプルなものだと言われることが多いですね。
なので、ある意味こういったまんがで要点を理解するのは理にかなっているのかもしれません。こちらのまんが版でも紹介されている数式は限られたもの。
主張はシンプルなんです。
さて、そのピケティの主張をよりよく理解するためには、まず既存の経済学で、格差がどう扱われていたかを簡単に知っておくといいかもしれません。
まずこれまでの経済学では、基本的には、成長することで格差は自然と縮まると考えられていました。サイモン・クズネッツという経済学者がこのことを、データをもとに発見しました。
そして、この発見などをベースに経済学が主に取り組んできたのは、経済全体のパイをいかに最大化するか、ということ。(これは経済学で格差の問題を無視、あるいは軽視してきた事を意味するわけではありません)
パイ自体が大きくなれば、取り分の程度はあれど、成長していくことで格差は収縮していき、平均的にみんなが豊かになれる、というのが大テーマだったと思います。
経済学はもっと多様で格差も積極的に扱っているとは思いますし、もしかしたらこれはちょっと単純化しすぎなのかもしれません、ただそれは私の理解不足なので至らなかったらすみません。
とはいえ、この考え方自体は経済学の取り組みの流れとして基本的なところだと思います。
その基本的なところに疑問を投げかけたのがピケティだったのだと思います。そしてだからこそ、これほど話題になったのだと思います。
ピケティの言いたかったこと
過去の経済学の主張と比較しながら、ピケティの主張を4段階でザザッと私なりにまとめてみたいと思います。
【既存の説】
まずパイを最大化し”効率”を目指そう。話はそれからだ。
神の見えざる手、市場のメカニズムに従えば、みんなの利益は最大化する。
再分配の仕方をうまくやって、経済成長すれば格差は自然となくなるよ、オッケー!
【ピケティ】
<1>
r>g(資本収益率r>経済成長率g)
導き出されたこの不等式が格差の拡大を主張する根本要因。
これは、資本をたくさん持ってる人が投資して、投入された資本に対して得ることができる収益の率(だいたい5%くらい。100投入して5の利益)の方が、経済成長してみんなが労働で稼ぐ所得が増えていく比率より、大きいよ。
これは理論じゃなくて歴史的な事実だよ。
だから経済成長で資本を持つ人と、持たない人が格差を埋めるのはそもそもちょっと限界あるっぽい。
だからと言って成長は否定しないよ。成長は確かに格差を埋める効果はある。
ただし歴史的な事実によると平均成長率は、各国の政府が掲げる目標には届かないし実は結構低いから、経済成長以外の格差の縮小も現実もうちょい視野に入れるべき。
<2>
また、その資本は、ますます今後増加していく方向に向かってるっぽい。
資本/所得比率というけど、国民資本の国民所得に対する比率、例えると年収と貯金の比率はどんどん大きくなっている。
先進国では、平均して国の年収の5〜6倍の貯金、すなわち資本の蓄えがあるイメージ。
1970年から2010年にかけてこの資本/所得比率は事実として増大傾向だし、
その上r>g(資本収益率r>経済成長率g)だから、資本をもつ人が輪をかけて豊かになっていく恐れがあるのでは。
これはなんとかしたほうがいいんでは?
<3>
また資本をもつもの持たざるものの格差だけでなく、労働によって得る収入の格差も広がっているよ。特にアメリカは大きいよ。
とはいえ、
資本所得格差(資本からの収入の格差)>労働所得格差(労働から得る収入の格差)
なので、資本所得の格差のほうが大きいことも忘れずに。
<4>
対策としては、税金は有効。累進資本課税がいいんじゃない?たくさん持ってる人から多くとる、持たない人からはあまりとらない。これを世界が協力してやればタックスヘイブンみたいな税逃れもできにくいしいいと思う。他にも経済成長やインフレは有効だし、格差を縮小する方法はいろいろ考えられる。
まとめ
ということで、以上のような内容が「21世紀の資本」で主張される、格差の問題の核になるのだと思います。とはいえ、そもそも私は原著は読んでない不届きものですし、原著を分かりやすく説明してくれた、まんがを読んで、そこからさらに私の見方を示しただけですので、実際には、この紹介したまんが版か原著を読まないと、理解は難しいと思います。
既存の経済学の大前提へ疑問を投げかけたピケティ。
反論も多くあるようですが、反論を乗り越え、取り込みながら今後このピケティさんの発見、知見が洗練されていって、我々人類の未来をより豊かなものにしてくれるものと信じています。
私なりに、このまんが版を読んで核はつかめたので、たいへん楽しく有意義でした。
| まんがでわかるピケティの「21世紀の資本」 (まんがでわかるシリーズ) | ||||
|