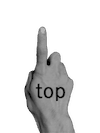Contents -目次-
資本主義とか自由市場経済って不公平じゃないの?公平ってどういうこと?

私は、アメリカの経済学の教授である、グレゴリー・マンキューという人が書いた経済学の教科書を読むのがとても好きです。全編において、目からウロコのトピックだらけで、世の中の見方、経済の見方が変わります。本当にためになります。もうなんというか、アレです、義務教育に取り入れるべきレベルです。世の中経済に関して敬遠しすぎ!経済学のイメージ悪すぎ!経済学というとすぐに、金持ちが儲かるだけ、とか、お金が儲かればなんでもいいのか!とか、資本主義終わってるから意味ない、とか言われますけど、そんなことないです。もったいない!こんなに面白いのに!無条件に、そして無批判に敬遠してしまうその姿勢こそが、今の日本の経済の停滞を長引かせてる一因とも思えてしまいます。なぜなら、経済学というのは有用な”道具”であって、ちゃんと理解して使えばこれほど有用なものはないからです。今よりも多くの人々が、経済に関しての適切な知見を共有できれば、世の中はもっと良くなる余地はあるのではないでしょうか?実は、ニュースや新聞ですら、経済学の教科書レベルのことを間違えて報道していることもしばしばです。
大事なのは、経済学のたくさんのトピックはとびきり頭のいい人が、まさに経済学でいう”効率”(なるべく損する人が少なく、なおかつ最大限多くの人が幸せになれる状態)を目指して一所懸命考えて、生み出されたアイデアである、ということです。
だからちゃんと使えば、できる限り多くの人々が幸せになることを可能にするアイデアばかりなのです。
さてそんな、素晴らしい知見に満ち溢れたマンキュー先生の教科書に、「消費者、生産者、市場の効率性」という章があります。
その中で語られていることは、一秒でいうと「市場とそのメカニズムは素晴らしい」ということです。
どう素晴らしいかというと、市場のメカニズムによる分配は、
- 効率性
- 公平さ
において、他の分配方法よりも優れているから、というのが理由になります。
効率性において優れている、というのはちゃんと理解したつもりでしたが、ずーっと公平さっていうのは本当かな?どうしてかな?と、腑に落ちない部分がありました。
だって市場経済が公平だ、とマンキュー先生にいくら言われても、、、
世の中には自分も含めあまり豊かじゃない人がたくさんいて、既得権はのさばり、生まれつきお金持ちの人もいるし、政治家は私腹を肥やすし、不公平に満ち溢れてる
じゃないですか。もうなんというか、気持ちはパンクロックですよ。
それなのにどうして公平なんだろうか?とずっと疑問だったのです。
ところが、今日読んだ本のおかげで、”市場の公平さ”というのがすんなり納得できたのです!
備忘録ということで、自分なりにまとめておきたいと思います。
市場による分配の方法以外にどんな方法がある?
世の中には、ありとあらゆる希少な資源(なんでも人参でも、服でも、CDでも石油でも)が存在します。無限なものなんてありませんから、あらゆるすべてが希少な資源、です。
その資源を分配する方法の一つが資本主義に基づいた『自由(完全に競争的な)市場』ということになります。
そしてそれこそが最も公平で、人々の利益を最大化する分配の方法だとされています。
他にどんな分配の方法があるか?というと、例えば極端な例としてはいわゆる「計画経済」と言われるものが挙げられます。そこでは希少な資源は、市井の個人や企業の自由な意思決定に基づいて分配されるのではなく、国家の指令と計画のもとに商品の生産・流通・販売や財の分配が行われます。
また、他には独裁者が特権的な権力で、経済を支配してしまい、人々にはわずかな分け前しか与えられない、などという分配も考えられます。
そもそも資本主義経済を前提とした、「市場」のメカニズムによる分配以外にも、このような方法が存在するのです。
なぜ「市場」による分配は優れているのか?
さて、前述のような他の分配の方法に比べて、経済学においては、この「市場」の分配というものが、もっとも効率的で公平であると信じられています。ではなぜ「見えざる手」の市場のメカニズムはもっとも効率的で公平なのでしょうか?

「効率的」とは
まず効率的、ということから考えたいと思います。
経済学において「効率的」というのは、その経済において市場に参加する人々の全体のパイがもっとも大きくなる状態、ということです。
そして、「市場」において機能する、需要と供給のメカニズムが、人々に分配される希少な資源の、量と価格の調整を行うことによって「効率的」な状態が達成されることが明らかになっています。
人気があり、数が少ないものは高くなり、その逆は安くなる。などなど、当たり前のようですが、こういったメカニズムが人々に効率をもたらしているのです。
では、なぜそうなるのか?というのは需要供給曲線、というものを描けばすぐに理解できるのですが、あえて、とても簡単に言うと市場による分配の方法は、
- もっともその財・サービスを欲しいと思い、また高い価値をつける人から順に財・サービスを分配でき、
- もっともその財・サービスを生産するのに低いコストで生産できる生産者から順に財・サービスの生産を割り当てることができる。
ということが可能なのです。
そしてこの事が、消費者/生産者余剰というもので測られる、経済全体のパイを最大化する=「効率的」である、ということになります。
「市場」のもたらす公平さとは
また「公平性」という点でも「市場」のメカニズムは優れているとされています。
私にはそこのところがすんなりとは理解できなかったのですが。
とはいえ例えば、仮に他の分配方法だとどうでしょうか?独裁者の個人的な考えで、財・サービスを割り当てたらどうでしょうか。気まぐれに持つもの、持たざるものを振り分けられるのでとても不公平です。またそんな世界では、独裁者に取り入ることが自分の幸福につながるため汚職や、腐敗を生み出すこと間違いなしです。
さらに他の分配方法ではどうでしょうか?先着順で分配?あみだくじで?いろいろな方法が考えられます。でもこれらは、どれも財・サービスの分配としては決して公平とは思えません。
残念ながらある種の不公平さは絶対に無くせない、というのも真理だと思います。
しかし私にとってはここが一番重要なのですが、
「市場」による需要と供給のメカニズムによってもたらされた「価格調整のメカニズム」による分配が、人々に最大限の公平さをもたらしていること、
そしてこれが事実であるということ。
そうです、事実として実際に市場経済は人々に公平さをもたらしているのです。
実際、人類がもっとも豊かになったのは資本主義に基づいた自由市場経済を導入してからです。
そのことは、この本を読むとよくわかります。
| 【反資本主義の亡霊 (日経プレミアシリーズ) |
||||
|
資本主義に基づく自由市場経済は事実として公平か、不公平か
『反資本主義の亡霊』によると、格差の問題はもちろんありますが、資本主義に基づいた自由市場経済がその経済の参加者全員の平均所得を飛躍的に引き上げていることが、2000年にわたる購買力平価GDPの統計的なデータから明らかになっています。
「マディソン教授のデータ」:[原田泰 「反資本主義の亡霊」日本経済新聞出版社 .p17]
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/publications/wp4.pdf
(The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version.)
産業革命以後、資本主義に基づいた自由市場経済を導入した国では、みんなの生活水準が”飛躍的に”上昇し豊かになっているのです。
もちろんその中でもお金持ちの人、貧しい人の差はありますが、少なくとも全員が豊かになっている。
そして私が思ったのは、
少なくとも、全体として人々の生活水準が向上している、これこそがある種の公平さ、と言えるのではないか?
ということです。これなら私も理解できる。
特定の人々だけが、大金持ちになることもあるが、それでも全体として豊かになっているという事実。
そしてもう一つ事実としてはっきりしているのは、資本主義以外の方法はこのような全体の平均的な生活水準の引き上げをもたらすことはなかったということ。そして、歴史的にも資本主義に基づく自由市場経済以前(だいたい産業革命以前)は豊かな貴族や王はある程度余裕のある生活をしていたが、それですら今の先進国の普通の人の暮らしに比べても不自由で、なおかつ当時の貧しい人は相対的に今の貧しい人に比べてはるかに貧しく、もっと格差は大きかった、ということ。
それに比べれば、今現在の我々の暮らしははるかにマシです。お金持ちになろうと思えば、チャンスはあります。階級社会のように階層が固定されているわけではありません。誰でも企業を起こすこともできます。確かに、相対的に公平なことは間違いありません。
それでも残る格差の問題
我々は事実として、人類が経験してきた過去の時代のどんな経済のあり方よりも、相対的に、現在の資本主義経済に基づいた市場経済の方がより公平だと言えます。
しかしそれでも完全ではありません。未だ残る不公平さ、格差というのは一体どんなものなのでしょうか。
格差に関しては、ピケティの『21世紀の資本』が近年大変話題になりました。
ピケティの主張は、資本を持ってる人が豊かになるスピードは、持ってない人よりもとても早いよ、ということでした。そして、「資本/所得比率」と言われる、資本の所得に対する比率は増加傾向にあり資本の蓄積が進んでいるよ、そして労働によって得られる所得の格差も大きくなっているよ。というものでした。
そんなことないんじゃないか、という反論もありますが、これもデータから導き出された一つの事実。留意しておく必要がありますよね。
一方、市場はみんなのパイ、全体の取り分は最大化することができるし、人々みんなの生活水準を時間を通じて平均的に引き上げることはできる。しかし、そもそもその経済の中の人々の間の格差を埋めるのは市場だけでは限界がある、ということも言われています。再分配をどうするか。
いわゆる勝ち組と負け組がどうしても出てきてしまうし、むしろその再分配が適切になされることが難しい状況でパイを最大化することは格差を大きく広げることにつながるのではないか。などなど、、、
近年ますます人々の関心を集めている、格差の問題。
資本主義に基づく市場経済は、相対的に人々に公平さをもたらし、人々を豊かにしたということは、よく理解できた気がします。
しかしそれで全て完璧、というわけではないし、さらに改善していくべきところもたくさんあるのだと思います。
不公平や不平等の問題はとても難しい問題ですよね。
そもそも公平とはどういった状況を指すのか。完全な公平さは存在するのか。誰かが他の人と比べて、富を持つことが許されるのはどのくらいのレベルまでなのか。
価値観が大きく入り込むことが、格差や不平等の問題を解決することの、根本的な困難さをもたらしているように思えます。
それでも事実として、現在の資本主義に基づく市場経済は、現在において人々が取りうる最もベターな選択肢の一つ、ということは言えそうです。
もし経済学について基本的なことが知りたければまずこちらがおすすめです。少し古いですが内容は普遍的に有用なものばかり。ミクロ、マクロの重要なトピックをコンパクトにまとめてあります。
| マンキュー入門経済学 | ||
|
| by ヨメレバ |
私はマクロ経済についてもう少し知りたかったので、こちらの、入門編に続いてマクロ編を買いました。失業、雇用の問題、金融、、、本当に素晴らしい知見がたくさん掲載されています。ぜひ。
| マンキュー経済学 II マクロ編(第3版) | ||||
|